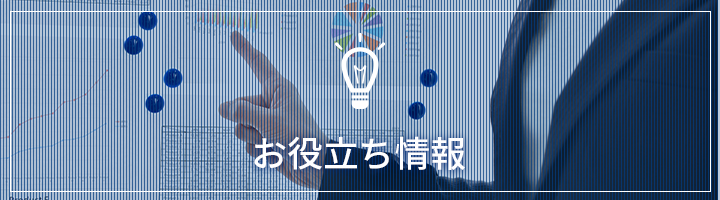11月は「過労死等防止啓発月間」 労務管理ポイント
2025年11月5日
11月は「過労死等防止啓発月間」
~企業が取り組むべき労務管理ポイント~
毎年11月は厚生労働省が定める「過労死等防止啓発月間」とされ、長時間労働の是正や賃金不払残業等の解消に向けた重点的な監督指導等が実施されます。
働き方改革が進む一方で、長時間労働やメンタルヘルス不調により労災申請は増加傾向にあり、企業としての取り組みはますます重要になっています。
これから迎える12月~1月は、繁忙時期となり残業時間が増えやすく、健康障害や労務トラブルが起こりやすい季節です。この啓発月間を機に、あらためて企業がおさえておきたい労務管理のポイントをまとめました。
1、長時間労働と過労死等の関係について再確認
■過労死の定義
①業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
②業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
③死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
■過労死ラインとされる時間外・休日労働時間の目安(脳・心臓疾患に係る労災認定基準)
● 週40時間を超える時間外・休日労働がおおむね45時間を超えて長くなるほど業務と発症との関連性は徐々に強まる。
● 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価される。
業務の過重性は労働時間のみによって判断されるものではなく、就労態様等の負荷要因も含めて総合的に評価されるものであるため、時間外・休日労働時間の把握はもちろん、単純に時間の長さだけで判断せず、勤務時間の不規則性、業務量、頻繁な出張の有無、緊張や責任負担が強い業務の有無、ハラスメント等による心理的負荷状況、職務環境等、総合的な管理が必要です。
2、労働時間の適正把握
厚生労働省の資料では、過重な長時間労働や割増賃金の未払いなどの問題の背景には、労働時間を適切に管理できていないケースがあるとし、適正な労働時間の把握の重要性があげられています。使用者には、従業員の労働時間を適切に管理し、適正に把握する義務があります。適正把握できていない場合は、早急に体制を整備しましょう。また、月末しか労働時間を確認していないという運用では、月中における労働時間の調整や特別条項の発動手続きを適切に行うことができませんので、こちらも改善が必要です。
3、36協定の締結・周知、及び運用の見直し
法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合、又は休日出勤をさせる場合は、36協定を過半数労働組合(労働組合がない場合は過半数代表者(36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで投票、挙手等により選出する必要があります。))と締結し、労働基準監督署へ届け出ることが義務になっています。36協定がない場合は、時間外労働や休日労働をさせることができませんのでご注意ください。また、36協定があるからといって無制限に残業させられるわけではありません。
<確認すべきポイント>
● 36協定を適切に締結し、労働基準監督署へ届け出ているか。
● 36協定を従業員の見やすい場所へ掲示するなど、周知しているか。
● 実態が協定時間内に収まっているか。
● 特別条項が「常態化」していないか。
● 特別条項の発動手続きを正しく行っているか。
● 割増賃金が正しく計算・支給されているか。
特に特別条項は、本来“突発的・臨時的”な場合に発動できるものです。常態化している場合は改善が必要です。また、特別条項の発動手続きを踏んでいないケースが見受けられます。特別条項を発動するには、協定で定めた発動手続きを踏むことが必要ですので注意しましょう。
※特別条項とは・・・通常の時間外労働の上限(原則として月45時間・年360時間)を、臨時的、突発的な事情がある場合に限って一時的に超えることを認める特例の労使合意。(時間外労働は年720時間以内、時間外労働・休日労働の合計は単月100時間未満及び2~6か月平均80時間以内。原則の月45時間を超えることができるのは年6回まで)
4、メンタルヘルス対策の強化
精神障害の労災認定件数は年々増加しており、早期対応が非常に重要です。
<企業として取り組める対策例>
● ストレスチェック結果の適切な活用(高ストレス者に対する医師による面接指導の実施)
※労働者数50人未満の事業場にについても令和7年5月公布改正労働安全衛生法によりストレスチェックや高ストレス者への面接指導が義務付けられました。(施行は公布後3年以内)
● 管理職へのラインケア研修の実施
※ラインケアとは、管理職が部下の健康状態を把握し、職場の問題を改善し、不調の早期発見・早期対応を行うことです。
● 職場内でのハラスメント防止対策(ハラスメント防止や相談窓口の周知・研修実施等)
● 業務量の偏り等の把握や相談体制の整備
● 長時間労働者への医師の面接指導(対象者への積極的運用。管理監督者も対象)
メンタル不調の前兆を見逃さない体制づくりがポイントです。
5、長時間労働の早期発見とフォロー、及び事前対策
長時間労働は、放置するとメンタル不調や健康障害につながります。
時間外労働や休日労働が多い従業員の把握、年次有給休暇の取得が進んでいない従業員の把握、業務ミスや遅刻・欠勤状況、表情の変化等のラインケア等を通して、異変を早期に発見する仕組みを作りましょう。
異変を察知した場合は、業務量の調整、休息の確保(代休、年次有給休暇取得促進、勤務管インターバルの確保等)、配置転換、業務分散、面談の実施等、早急にまた柔軟に対応できる体制作りをしておくとよいでしょう。
事前対策では、心身の疲労を蓄積させない職場作りとして、年次有給休暇の計画的な取得促進、連続休暇の設定、インターバル制度の導入等も会社が取り組める有効な手段となります。また、業務の隔たり等の申告、体調不良やハラスメントの相談等、相談体制の整備・周知も大変重要となります。従業員が相談しやすい相談体制(相談窓口が適切に機能している)になっているかどうか等、定期的な検証・整備、周知等も有効だと思います。
6、まとめ
企業には、従業員の生命・健康を守る安全配慮義務があります。過重労働や健康悪化のサインを放置していた場合、損害賠償請求などの責任が生じることがありますので注意が必要です。
過労死防止は「仕組みづくり」と「早めの対応」が重要です。
厚生労働省は、過労死防止のための取組として、「長時間労働の削減、過重労働による健康障害の防止、働き方の見直し、職場におけるメンタルヘルス対策の推進、職場のハラスメント予防・解決、相談体制の整備等」をあげています。これらは過労死防止の為の取組だけではなく、従業員の定着や生産性向上にもつながる取り組みです。11月は、年末年始の繁忙に向けて、要員計画の見直し、担当者の業務偏りの是正、管理職への注意喚起等、過重労働防止の対策を実施するにも良い時期だと思います。
11月の啓発月間をきっかけに、自社の労務管理体制をあらためてチェックしてみてはいかがでしょうか。
詳細は下記、厚生労働省ホームページをご確認ください。