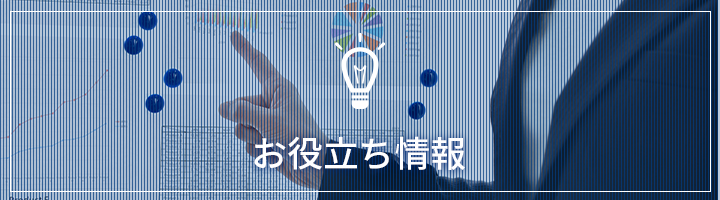育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等
2025年7月2日
改正育児・介護休業法
令和7年10月1日施行への対応準備はできていますか?
令和6年改正の育児・介護休業法については、令和7年4月1日からすでに施行されていますが、その一部については令和7年10月1日から施行されるものがあります。
直前に慌てることがないよう、令和7年10月1日施行の内容を確認し、準備を進めていきましょう。
<令和7年10月1日施行の内容>
1、柔軟な働き方を実現するための措置等
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置を講ずること
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、下記「選択して講ずべき措置」の①から⑤の選択肢の中から2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際は、過半数労働組合等(過半数労働組合がない場合は過半数代表者)の意見を聴く等の必要があります。
※意見聴取の方法に定めはありませんが、育児当事者等の意見を参考にしたり、アンケートを取る等、ニーズを適切に把握できるような方法により行うことが望ましいとされています。
※措置の内容は会社で統一とする必要はなく、各事業所別、業種別など、より実態に即した労働者が使用しやすいものとしてそれぞれ別の措置を選択することも可能です。
■選択して講ずべき措置
①始業時刻等の変更
1日の所定労働時間を変更せずに、始業・終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げることや、フレックスタイム制の適用等がこれに該当します。
②テレワーク等
1日の所定労働時間を変更せずに、月に10日以上テレワークを利用できるものがこれに該当します。テレワークは原則として時間単位で取得できるものとする必要があります。
③保育施設等の設置運営等
保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするものであり、その他これに準ずる便宜の供与には、事業主がベビーシッターを手配し、その費用の一部を補助することなどが含まれます。
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与
1日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上の休暇を、原則として時間単位で取得できるものにする必要があります。取得理由は、就業しつつ子を養育するのに役立てるものであれば、どのような目的に利用するかは労働者に委ねられるものです。この休暇は有給にすることまでを求められているものではないため、無給とする取り扱いでも問題はありません。
⑤短時間勤務制度
1日の所定労働時間を6時間とする措置を含むものとしなければなりません。
(2) 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認をすること
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になる前の適切な時期に、上記(1)で選択した構ずべき措置について次のとおり制度の周知と制度利用の意向の確認を個別に行う必要があります。
| 周知時期 | 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) 例:誕生日が4月20日の子の場合 1歳の3月21日から2歳の3月20日までの1年間 |
| 周知事項 | ①事業主が選択した講ずべき措置の内容(二つ以上)
②対象措置の申出先(例:人事部等) ③所定外労働、時間外労働、深夜業の制限に関する制度 |
| 個別周知・意向確認の方法 | ①面談、②書面交付、③FAX、④電子メール等のいずれかの方法により周知すること。
①はオンライン面談も可。③と④は労働者が希望する場合のみ可。④は電子メール等の内容を印刷することで書面を作成できるものに限る。 |
※施行日令和7年10月1日において、個別の周知・意向確認の対象となる子の範囲は、令和4年10月31日から令和5年10月30日までに生まれた子となります。
令和7年10月1日時点ですでに子が2歳11か月に達する日の翌日を過ぎている場合は、(2)の周知・意向確認の義務の対象にはなりませんが、子が3歳の誕生日から小学校就学前までの間に(1)の柔軟な働き方を実現するための措置については同様に利用できるものになります。
そのため、個別周知・意向確認の義務の対象外であっても小学校就学前の子を養育する労働者に対しては同様に個別の周知等をすることが望ましいとされています。
2、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1) 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者本人または配偶者の妊娠・出産等の申出を受けたときと、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
これは、「柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知と意向確認」とは別に行う必要があります。
| 意向聴取の時期 | ①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
②労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)②の適切な時期とは、「柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知と意向確認」と同様であるため、一緒に行うことも可能です。 |
| 聴取内容 | ①勤務時間帯(始業及び終業の時刻)
②勤務地(就業の場所) ③両立支援制度等の利用期間 ④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) 仕事と育児の両立を困難にしている要因がないかどうか確認します。 |
| 意向聴取の方法 | ①面談、②書面交付、③FAX、④電子メール等のいずれかの方法により周知すること。
①はオンライン面談も可。③と④は労働者が希望する場合のみ可。④は電子メール等の内容を印刷することで書面を作成できるものに限る。 |
(2) 聴取した労働者の意向についての配慮
事業主が、意向聴取した労働者の労働条件等を決定するにあたり、意向の内容を踏まえた検討を行い、その意向に配慮することを義務づけるものであり、必ず意向に沿った対応を講ずることを義務付けるものではありません。
自社の状況に応じて、可能な範囲で意向に沿うような配慮が必要ですが、結果として意向に沿うような対応ができるかどうかは事業主が決定するものとなります。
仮に、十分な検討の結果、意向に沿うことが難しい場合は、その理由等を労働者に説明する等丁寧な対応が求められます。
具体的な配慮としては、勤務時間帯・勤務地に係る調整、業務量の調整、両立支援制度の利用期間の見直し、労働条件の見直しなどがあげられます。
3、まとめ
10月1日施行日より義務が生じますので、それまでに次のような準備を進めることが考えられます。
①柔軟な働き方を実現するために講ずべき措置の選択にあたり、過半数労働組合等からの意見の聴取
②過半数労働組合等の意見聴取の内容を踏まえ、柔軟な働き方を実現するために講ずべき措置を2つ以上選択
③選択した内容に基づいて就業規則等の見直し
④10月1日時点で個別の周知・意向確認や個別の意見聴取をする対象者の抽出・準備
⑤個別の周知・意向確認や個別の意見聴取をする方法の検討や書面等の準備
⑥労使協定の締結(柔軟な働き方を実現するための措置は労使協定を締結することで、入社1年未満の従業員及び1週間の所定労働日数が2日以下の従業員を除外することが可能です。除外する場合は労使協定の締結が必要です。)
令和3年改正(令和4年4月1日施行)で既に義務となっている個別の周知・意向確認は育児休業等の制度についての周知と意向確認です。
令和6年改正(令和7年10月1日施行)で追加される個別の周知・意向確認は、柔軟な働き方を実現するための措置についての周知と意向確認、及び仕事と育児の両立に関する意向聴取です。
それぞれ、タイミングや目的・内容が異なりますので、混同しないように整理しておきましょう。
詳細は下記厚生労働省のホームページをご参照ください。