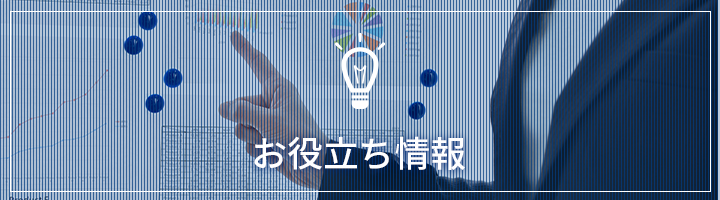出生後休業支援給付金とは?
2025年4月2日
出生後休業支援給付金とは?
~令和7年4月1日、新しい育児休業等給付が始まります~
これまでの出生時育児休業給付金、育児休業給付金に加え、令和7年4月1日からは、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金の2種類の新しい給付金が始まります。
今回は出生後休業支援給付金とはどのようなものか、従業員からの質問に対応できるよう概略をつかんでいきましょう。
1、出生後休業支援給付金とは
支給期間は最大で28日間です。
あくまで育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の上乗せの給付ですので、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給要件を満たしていることが前提となります。
(1)支給要件
① 出生時育児休業給付金が支給される出生時育児休業(産後パパ育休)を通算して14日以上取得した被保険者であること、又は、育児休業給付金が支給される育児休業を対象期間に通算して14日以上取得した被保険者であること。
※対象期間とは・・・
子の出生日又は出産予定日のうち早い日から、子の出生日又は出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間
<被保険者が産後休業をした場合(母親かつ子が養子でない場合)>
子の出生日又は出産予定日のうち早い日から、子の出生日又は出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日までの期間
② 被保険者の配偶者が、出生日又は出産予定日のうち早い日から、子の出生日又は出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間に通算して14日以上の育児休業又は出生時育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
※配偶者の育児休業を要件としない場合とは・・・
③被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
④配偶者が無業者
⑤配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者ではない
⑥配偶者が産後休業中
⑦1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
上記⑦の1~6以外の理由とは、具体的にどのような場合か・・・
(厚生労働省の育児休業給付Q&Aより)
②出生時育児休業の申出をすることができない有期雇用労働者であるため
③労使協定に基づき事業主から育児休業の申出又は出生時育児休業の申出を拒まれたため
④公務員であって育児休業の請求に対して任命権者から育児休業が承認されなかったため
⑤雇用保険被保険者ではないため、育児休業給付を受給することができない(共済組合の組合員である公務員の場合は除く)
⑥短期雇用特例被保険者であるため、育児休業給付を受給することができない
⑦雇用保険被保険者であった期間が1年未満のため、育児休業給付を受給することができない
⑧雇用保険被保険者であった期間は1年以上あるが、賃金支払いの基礎となる日数や労働時間が不足するため。育児休業給付を受給することができない
⑨配偶者の勤務先の出生時育児休業又は育児休業が有給の休業であるため、育児休業給付を受給することができない(有給でなければ出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を、期間内に通算して14日以上取得している必要があります。)
※令和7年4月1日より前から引き続いて産後パパ育休又は育児休業を取得している場合は、令和7年4月1日以降の対象期間だけで、上記①及び②の通算14日以上の要件を満たす必要があります。
(2)支給額
上乗せで支給されるものですので、仮に出生時育児休業を取得した場合は、下記のようになります。
<出生時育児休業給付金の額>
休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%
<出生後休業支援給付金の額>
休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
合計80%
※支給額には上限があります。
(令和7年7月31日までの休業開始時賃金日額の上限は15,690円です。毎年8月1日に改定があります。)
※出生後休業支援給付金が支給される期間に賃金の支払いを受けた場合、減額処理はありませんが、育児休業給付や出生時育児休業給付が支給されないときは、出生後休業支援給付金も支給されません。
2、まとめ
女性の場合は産後8週間の産後休業を経てそのまま育児休業に入るケースが多いと思います。
そのような場合、配偶者も産後パパ育休を14日以上取得していると、夫婦それぞれの育児休業給付や出生時育児休業給付に上乗せの給付がされるということになります。
これにより、4月1日以降に育児休業給付や出生時育児休業給付の申請をする際には、配偶者の状況も確認することが必要となります。
4月1日より前から引き続き育児休業又は出生時育児休業を取得している場合は、4月1日以降の日数のみで14日以上の休業がある場合に対象になりますので、あわせて確認をするようにしましょう。
従業員からの質問も増えてくると思います。きちんと説明できるように、また確認不足や手続き漏れ等で従業員に不利益が生じないように注意しましょう。
次回は、同じくこの4月1日から開始になる「育児時短就業給付」について取り上げたいと思います。
手続き方法等、詳細は下記をご確認ください。