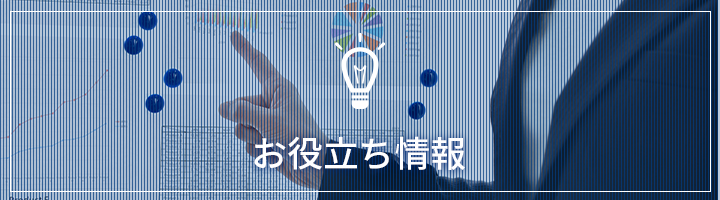育児時短就業給付金とは?
2025年5月8日
育児時短就業給付金とは?
~令和7年4月1日、新しい育児休業給付が始まっています~
これまでの出生時育児休業給付金、育児休業給付金に加え、令和7年4月1日からは、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金の2種類の新しい給付金が始まっています。
今回は育児時短就業給付金とはどのようなものか、概略をつかんでいきましょう。
1、育児時短就業給付金とは?
雇用保険の被保険者が2歳未満の子を養育するために、所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下する等一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。
2、育児時短就業給付金の概要
(1) 受給資格
① 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者であること。
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと(※)、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月以上あること。
※育児休業終了日の翌日から時短就業を開始すること、又は育児休業終了日と時短就業開始日の間が14日以内の場合をいいます。
(2) 各月の支給要件
① 初日から末日まで続けて被保険者である月。
※月の途中で退職(資格喪失)した場合は、その月は支給対象になりません。
② 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月。
③ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月。
④ 高年齢雇用継続給付の受給対象になっていない月。
(3) 支給対象となる時短就業
支給対象となる育児時短就業とは1週間当たりの所定労働時間を短縮する措置であり、1日当たりの所定労働時間を短縮することで1週間の所定労働時間が短縮される場合だけでなく、次のような場合も含まれます。
① 1週間の所定労働日数を減らした結果、1週間の所定労働時間が短縮されるもの。
② 育児介護休業法に基づく短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置)に限らず、2歳未満の子を養育するために1週間の所定労働時間を短縮するもの。
③ 被保険者が子を養育するために短時間正社員やパートタイム労働者等に転換、転職したことにともない、1週間の所定労働時間が短縮されるもの。
(注)短縮にあたって上限や下限等の制限はありませんが、雇用保険の被保険者が受けることができる給付金ですので、雇用保険の被保険者資格を喪失しない範囲であることが必要です。(1週間の所定労働時間が20時間以上)
<特別な労働時間制の適用をうけている場合の支給対象となる育児時短就業>
・フレックスタイム制・・・清算期間における総労働時間を短縮するもの。
・変形労働時間制・・・対象期間の総労働時間を短縮するもの。
・裁量労働制・・・みなし労働時間を短縮するもの。
・シフト制・・・実際の労働時間に基づいて1週間当たりの平均所定労働時間を算定し、短縮が確認できるもの。
※あくまで1週間の所定労働時間を短縮するものであり、残業時間が減っただけのような場合は対象にはなりません。
(4) 支給対象期間
支給対象月・・・原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各歴月について支給されます。
(例)2025年4月21日~2026年3月20日まで時短就業する場合は、2025年4月(4/21が属する月)~2026年3月(3/20が属する月)までが支給対象月になります。
但し、次の①~④の日の属する月までが支給対象月となります。
① 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
※2歳に達する日とは、2歳の誕生日の前日
② 産前産後休業、育児休業、介護休業を開始した日の前日
③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日
④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日
(5)支給額
① 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額※①の90%以下の場合
→支給対象月に支払われた賃金額×10%
(計算例)
育児時短就業開始時賃金月額:300,000円(300,000円の90%は270,000円)
支給対象月に支払われた賃金額:200,000円 の場合
支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下
支給額=200,000×10%=20,000円
② 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額※①の90%超~100%未満の場合→支給対象月に支払われた賃金額×調整後の支給率
支給率={9,000×育児時短就業開始時賃金月額÷(支給対象月に支払われた賃金額×100)-90}÷100
(計算例)
育児時短就業開始時賃金月額:300,000円(300,000円の90%は270,000円)
支給対象月に支払われた賃金額:280,000円 の場合
支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%超、100%未満
{9,000×300,000÷(280,000×100)-90}÷100=0.06428…6.43%(四捨五入)
支給額=280,000×6.43%=18,004円
③ 支給対象月に支払われた賃金と、①又は②による支給額の合計額が支給限度額を超える場合
→支給限度額※②-支給対象月に支払われた賃金額
(計算例)
育児時短就業開始時賃金月額:470,700円(上限額)(470,700円の90%は423,630円)
支給対象月に支払われた賃金額:420,000円 の場合
支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下
420,000×10%=42,000円
420,000+42,000=462,000円(支給限度額の459,000円を超えてしまう)
支給額=459,000-420,000=39,000円
(計算例は厚生労働省のホームページを引用)
※①育児時短就業開始時賃金月額とは・・・育児休業開始時賃金月額の考え方と同様です。
育児時短就業開始前直近6か月間(原則として賃金支払基礎日数が11日以上ある月)に支払われた賃金の総額を180で除して得た額(育児時短就業開始時賃金日額)に30を乗じたもの。(育児休業から続けて育児時短就業を開始した場合は、育児休業開始時賃金日額が育児時短就業開始時賃金日額とされます。)
育児時短就業開始時賃金日額・月額には上限、下限が定められています。
令和7年7月31日までの育児時短就業開始時賃金月額上限額470,700円(賃金日額上限額15,690×30)、下限額:86,070円(賃金日額下限額2,869円×30)。毎年8月1日に改定。
※②育児時短就業給付金には支給限度額と最低限度額が定められています。
令和7年7月31日までの支給限度額459,000円、最低限度額2,295円。毎年8月1日に改定。
支給対象月に支払われた賃金額が休業開始時賃金月額の100%以上の場合や、支給限度額以上の場合、給付金は支給されません。
また、上記①~③により算定された金額が最低限度額以下の場合も給付金は支給されません。
3、まとめ
育児時短就業給付金は、育児時短就業により低下する賃金部分への補助的な意味合いの給付金となります。
この給付金は令和7年4月1日以降に育児時短就業を開始した方が対象になりますが、令和7年4月1日より前から育児時短就業に相当する就業を行っている場合は、令和7年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなします。
そのうえで受給資格・各月の支給要件を満たす場合は、令和7年4月以降の各月を支給対象月として支給されることになります。
令和7年4月1日より以前から育児時短就業を開始している場合は、令和7年4月1日以前6か月の賃金総額から育児時短就業開始時賃金月額を算出するため、すでに短時間就業により減少した賃金を含んで育児時短就業開始時賃金月額が決定されることになります。
そのため、育児時短就業開始時賃金月額からの賃金の減少幅が少ない、減少しない等、受給資格はあっても、各月の支給要件を満たさない、又は仮に支給要件を満たして支給された場合でも、給付金額が少ないなど、この給付金のメリットを十分に享受できない可能性がありますので、従業員から質問を受けた場合は、そのことを念頭において説明するとよいでしょう。
2歳までの給付金であること、また育児休業から引き続き時短就業を開始する場合には、育児時短就業開始時賃金の届出が省略できることなどを鑑みると、育児休業後は育児時短就業により復帰するというケースが増えてくることも予想されます。
今後、育児時短就業の申出があった際には、時短就業になったことが確認できる書類として、時短後の労働時間や日数を明示した労働条件通知書等を作成しておくと良いでしょう。
育児時短就業になるとその分だけ賃金が減少するケースが多いため、この給付金が創設されたことで、育児時短就業を検討する方が増えていくことも予想されます。
また、すでに育児時短就業を開始している従業員から、自分が対象になるかどうかの問い合わせがあるケースも見受けられます。
正しく説明できるよう情報を整理しておきましょう。
手続き方法等、詳細は下記をご確認ください。