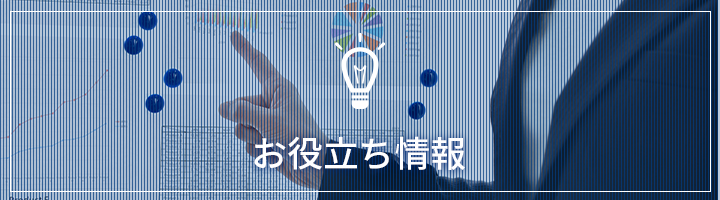-
【YouTube動画】年次有給休暇についてアップいたしました。
2025年10月29日
【 年次有給休暇の制度 】 ・年次有給休暇の正社員の付与要件 ・年次有給休暇のパート・アルバイトの付与要件 ・年次有給休暇の時季変更権、年次有給休暇の時季指定義務 ・年次有給休暇の計画的付与 ・年次有給休暇の時間単位付与 ・年次有給休暇の時効、年次有給休暇に対して支払うべき賃金 上記ついて簡単にまとめました。 ぜひ、制度利用の際のご参考にしてください。
-
令和8年度 在職老齢年金制度の支給停止調整額が変更されます
2026年2月3日
令和8年度
~在職老齢年金制度の支給停止調整額が変更されます~
(令和7年の年金制度改正による大幅引き上げ)
令和8年4月より、在職老齢年金制度の支給停止調整額が、65万円に変更されます。
令和8年1月23日、厚生労働省のホームページにおいて、「令和8年度の年金額改定」についてのPress Releaseが掲載されました。その中で、令和8年度の在職老齢年金支給停止調整額が65万円になることが公表されています。
■変更内容
支給停止調整額 令和7年度:51万円 ⇒ 令和8年度:65万円
■引き上げの背景
高齢者の就業活躍の重要性と年金の支給停止による就業調整等の問題を背景に、令和7年の年金制度改正において、令和8年4月からの支給停止調整額が、令和6年度支給停止調整額50万円に対して62万円まで引き上げることが示されていました。62万円は令和6年度水準に対しての価格になりますので、その後の賃金変動率に応じて令和8年度がいくらになるのか注目していましたが、令和7年に用いた名目賃金変動率(2.3%)と令和8年度に用いる名目賃金変動率(2.1%)に応じて、65万円となることが公表されました。
※年金制度改正 ・・・(令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が国会に提出され、衆議院の修正を経て、令和7年6月13日に成立しました。)
■在職老齢年金制度とは…
働きながら(厚生年金に加入している又は加入義務の年齢を過ぎても加入要件を満たすような働き方をして給与等を得ている場合)老齢厚生年金を受けることができる人については、給与等(賞与含む)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計額(1か月当たり)が支給停止調整額を超える場合には、老齢厚生年金額について一部支給停止又は全額支給停止等の支給調整が行われます。これを在職老齢年金制度といいます。
■支給停止調整額とは…
給与等(賞与含む)と老齢厚生年金の合計額(1か月当たり)がこの金額までなら支給停止なく全額支給されるという基準額のことを「支給停止調整額」といいます。以前は60歳以上65歳未満と65歳以降では、支給停止調整額が異なっていましたが、令和4年4月の年金制度改正により、60歳以上65歳未満も65歳以上と同じ支給停止調整額に改正されています。この支給停止調整額は毎年4月に見直しがあり、令和8年度は、前年度の51万円から65万円に大幅に引き上げられます。
■令和8年度の在職老齢年金制度による支給停止計算方法
給与等(賞与含む)の1か月あたりの額と老齢厚生年金の1か月あたりの額の合計が65万円以下であれば年金は支給停止なく全額支給され、65万円を超えた場合は、超えた額の半分が支給停止になります。尚、老齢基礎年金は給与等に関係なく全額受給できます。
支給停止額 =( 総報酬月額相当額・・・① + 基本月額・・・② - 支給停止調整額(令和8年度は65万円))÷ 2
<計算例>
標準報酬月額34万円、1年間の賞与120万円、老齢厚生年金120万円とした場合
①総報酬月額相当額・・・44万円/月(標準報酬月額34万円+標準賞与額の1か月分(120万円÷12月))
②基本月額・・・10万円/月(老齢厚生年金の1か月分(120万円÷12月))
令和7年度の支給停止調整額:51万円、令和8年度の支給停止調整額:65万円により年金の支給停止金額は下記のようになります。
★令和8年3月まで・・・支給停止額=(44万円+10万円-51万円)÷2=1万5千円
1か月あたり1万5千円の老齢厚生年金が支給停止されます。
★令和8年4月以降・・・44万円+10万円は54万円となり、65万以下のため、支給停止はありません。
①総報酬月額相当額とは…
調整の対象となる月におけるその方の「標準報酬月額」と「その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額」を合算して得た額のことです。
※70歳以上の場合は、標準報酬月額に相当する額、標準賞与額に相当する額。
②基本月額とは…
老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額(加給年金を除く。基金代行額を含む。)を12月で除して得た額のことです。(老齢基礎年金は支給調整の対象外です。)
※加給年金は除いて在職老齢年金の支給停止額を計算しますが、老齢厚生年金の一部でも支給されていれば加給年金は全額支給され、老齢厚生年金の全額が支給停止されている場合は加給年金も全額支給停止になります。
■在職定時改定
令和4年4月の年金制度改正により、毎年9月1日に厚生年金に加入中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給権者について、前年9月から当年8月までの厚生年金保険加入期間を反映して、年金額を10月分(12月受取分)から改定する仕組みがとられています。これにより原則として年金額が年に1度増額改定されるため、報酬等に増額がない場合でも在職老齢年金制度による支給停止額には影響が出る可能性があります。
■まとめ
老齢年金を受給していても、加入要件を満たす場合、70歳までは厚生年金に加入し保険料を納めなければなりませんが、その分年金は増えていくことになります。
また、70歳以降厚生年金の加入義務がなくなっても厚生年金の加入要件を満たすような働き方を継続している限り、現行制度においては年齢の上限なく在職老齢年金制度による老齢厚生年金の支給調整は行われることになります。
不動産収入等、給与以外の収入も支給調整の対象に入るか等のご質問をよくいただきますが、支給停止計算方法からもおわかりいただけるように、現行の制度においては、年金と報酬との調整は標準報酬月額や標準賞与額を使用しますので、それ以外の収入は調整の対象外となります。また、支給停止されていても、将来年金を繰下げ受給する際には、繰下げ増額された老齢厚生年金を受け取れると誤解されているケースもあるかと思います。繰下げ受給で増額されるのは、受け取れる年金を受け取らずに繰下げした場合であり、支給停止されている部分については増額の対象外ですのでご注意ください。
在職老齢年金の支給停止調整額は、毎年4月に改定されますが、ここ数年の推移は、令和4年度が47万、令和5年度が48万、令和6年度が50万、令和7年度が51万円となっています。そして令和8年度は年金制度改正により65万と大幅な引き上げになりました。これまで支給停止になっていた方も、令和8年4月以降は支給停止にかからない可能性もあります。またこれまで支給停止を意識して就労制限されていた方は、就労制限を気にせずに働けるようになる可能性もあります。このように令和8年度の在職老齢年金支給停止調整額の改定は、令和7年の年金制度改正に伴う大きな変更内容となりますので、ぜひ注目してみてください。
働いて給与等を得ている方が老齢厚生年金を受給できるようになった時や、給与等を得ながら老齢厚生年金を受給している方が給与等を変更する場合等には、少なからず年金額への影響があるため、在職老齢年金制度をよく理解するとともに、毎年この時期は、支給停止調整額についても改定の内容をチェックするようにしましょう。
詳細は下記をご参照ください。
-
被扶養者の認定における年間収入の取扱い変更
2026年2月3日
健康保険の被扶養者の認定の年間収入について、今までは、扶養に入れたい家族の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、時間外労働に対する賃金等の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定していましたが、令和8年4月1日からこの年間収入の取扱いが変更になります。
◆労働契約の内容に基づく年間収入で判定
雇用契約書や労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額(※1)が 130 万円未満で、かつ、他の収入が見込まれず、
1.認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合(※3)
2.認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。
そのため、当該書類上に明確な規定がなく予め金額を見込み難い時間外労働に対する賃金等は年間収入の見込額には含まないこととなります。
労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。
※1 労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。
※2 認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円未満(ただし、障害年金などの給与以外の収入があると、この方法は使えません。)、認定対象者(被保険者の配偶者を除きます。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満となります。
※3 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、保険者がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。詳細は、厚生労働省、日本年金機構のホームページでご確認ください。
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて/日本年金機構
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて/厚生労働省
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて/厚生労働省
-
健康診断後の「医師等からの意見聴取」を忘れていませんか?
2026年1月7日
この時期になると、各企業で定期健康診断を終え、結果が返ってきているかと思います。
労働安全衛生法では、一定の条件に該当する従業員について、医師による就業上の措置に関する意見聴取を実施し、その意見に基づき必要な措置を講じることが義務づけられています。放置すると労務リスクの増大や行政指導につながるおそれがあります。「健診は実施した」「結果は配布した」・・・そこで完了としてしまっていませんか?健診後の医師等からの意見聴取が法律上の義務であることを知らない事業者が以外と多いのではないかと思います。せっかく健康診断を実施してもその後のフォローや義務が実施されずに終わっているのはとてももったいないと感じます。「知らなかった」、「やっていなかった」という場合は、この機会に内容を理解し、「健康診断後の医師等からの意見聴取」を確実に実施するようにしましょう。
1、健康診断の結果についての「医師等からの意見聴取」(労働安全衛生法第66条の4)
健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について産業医等の医師から意見を聞くことが必要とされています。意見の聴取は健康診断実施後の3か月以内に行う必要があります。
■医師の意見聴取とはどんな内容?
①就業区分及び就業上の措置について医師等の意見を求めます。
就業区分 内容 就業上の措置の内容 通常勤務 通常の勤務でよいもの 就業制限 勤務に制限を加える必要のあるもの 勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる。 要休業 勤務を休む必要のあるもの 療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。 ②作業環境管理及び作業管理を見直す必要がある場合には、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置についての意見を求めます。
■意見を聴く医師とは?
①労働者数が50人以上の事業場は、産業医から意見を聴くことが適当です。(※50人以上の労働者がいる事業場は産業医の選任義務があります。)
②労働者数が50人未満の産業医の選任がない事業場は、地域産業保健センターを活用するとよいでしょう。(各都道府県・地区ごとに窓口があります。)
地域窓口(地域産業保健センター)| JOHAS(労働者健康安全機構)
2、健康診断実施後の措置(労働安全衛生法第66条の5)
・医師等からの意見を勘案し、その必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じます。
・作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備
・医師等の意見の衛生委員会等への報告等
3、まとめ
健康診断は実施して終わりではなく、その後のフォローがもっとも大事です。法令順守はもちろん、働く人が長く健康に活躍できる職場づくりのため、「医師等からの意見聴取」を適切に実施しましょう。また、精密検査や保険指導を受けたり、個人的に医師に相談する行為等は、労働安全衛生法第66条の4で定める「医師等からの意見聴取」とは異なるものです。精密検査等とは別に、実施する必要があるものですので混同しないように注意しましょう。
詳細は下記、厚生労働省のホームページをご確認ください。
-
子ども・子育て支援金の徴収が始まります
2025年12月2日
令和6年6月12日に成立した子ども・子育て支援金制度の創設を内容に含む法律に基づき、社会全体で子ども・子育て世帯を応援していくため、児童手当の拡充をはじめとした抜本的な給付拡充の財源の一部に、「子ども・子育て支援金」が充てられます。
子ども・子育て支援金は、全国健康保険協会や健康保険組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度などの医療保険者が、健康保険料・介護保険料とあわせて徴収することになりました。
ここでは、企業での実務を中心にご案内します。
◆子ども・子育て支援金は何に使われますか?
支援金が充てられる事業は法律(子ども・子育て支援法)で以下のとおり定められており、これら以外の目的で使用されることはありません。
① 児童手当(高校生年代まで延長、所得制限の撤廃、第3子以降の支給額増額を実施)※令和6年10月から
② 妊婦のための支援給付(妊娠・出産時の10万円の給付金)※令和7年4月から制度化
③ こども誰でも通園制度(乳児等のための支援給付)※令和8年4月から給付化
④ 出生後休業支援給付(育児休業給付とあわせて手取り10割相当(最大28日間))※令和7年4月から
⑤ 育児時短就業給付(時短勤務中の賃金の10%支給)※令和7年4月から
⑥ 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置 ※令和8年10月から
⑦ 子ども・子育て支援特例公債(支援金の拠出が満年度化する令和10年度までの間に限り、①~⑥の費用の財源として発行)の償還金
◆開始時期は?
令和8年4月分(5月納付分)より、健康保険料・介護保険料とあわせて被保険者の給与から徴収し、事業主負担分をあわせて全国健康保険協会や健康保険組合などの医療保険者へ納付します。
全国健康保険協会や健康保険組合などの医療保険者は、子ども・子育て支援金の徴収を代行し、国に納付します。
◆負担額はどのくらいになる?
標準報酬月額 × 支援金率 = 1人当たりの負担額
○負担額は、健康保険や介護保険と同じように標準報酬月額を基に算出しますので、被保険者の収入により異なります。
○1人当たりの負担額を、被保険者と事業主で折半して負担することになります。
○支援金率は、国が一律の支援金率を示すことになっており、令和8年からスタートし、令和10年度まで段階的に上がることが想定されます。
◆給与明細に表示する必要はありますか?
被保険者から保険料を徴収するときに保険料額の内訳として子ども・子育て支援金額を表示することは法令上の義務ではありませんが、社会全体で子どもや子育て世帯を応援する支援金制度がスタートしたことを知ってもらうためにも、給与明細書に表示することが望ましいでしょう。
また、給与明細書に表示することが難しい場合も、保険料の一部に子ども・子育て支援金が含まれることについて、従業員に周知をしましょう。
その他、詳細は下記ホームページでご確認ください。
-
11月は「過労死等防止啓発月間」 労務管理ポイント
2025年11月5日
11月は「過労死等防止啓発月間」
~企業が取り組むべき労務管理ポイント~
毎年11月は厚生労働省が定める「過労死等防止啓発月間」とされ、長時間労働の是正や賃金不払残業等の解消に向けた重点的な監督指導等が実施されます。
働き方改革が進む一方で、長時間労働やメンタルヘルス不調により労災申請は増加傾向にあり、企業としての取り組みはますます重要になっています。
これから迎える12月~1月は、繁忙時期となり残業時間が増えやすく、健康障害や労務トラブルが起こりやすい季節です。この啓発月間を機に、あらためて企業がおさえておきたい労務管理のポイントをまとめました。
1、長時間労働と過労死等の関係について再確認
■過労死の定義
①業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
②業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
③死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
■過労死ラインとされる時間外・休日労働時間の目安(脳・心臓疾患に係る労災認定基準)
● 週40時間を超える時間外・休日労働がおおむね45時間を超えて長くなるほど業務と発症との関連性は徐々に強まる。
● 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価される。
業務の過重性は労働時間のみによって判断されるものではなく、就労態様等の負荷要因も含めて総合的に評価されるものであるため、時間外・休日労働時間の把握はもちろん、単純に時間の長さだけで判断せず、勤務時間の不規則性、業務量、頻繁な出張の有無、緊張や責任負担が強い業務の有無、ハラスメント等による心理的負荷状況、職務環境等、総合的な管理が必要です。
2、労働時間の適正把握
厚生労働省の資料では、過重な長時間労働や割増賃金の未払いなどの問題の背景には、労働時間を適切に管理できていないケースがあるとし、適正な労働時間の把握の重要性があげられています。使用者には、従業員の労働時間を適切に管理し、適正に把握する義務があります。適正把握できていない場合は、早急に体制を整備しましょう。また、月末しか労働時間を確認していないという運用では、月中における労働時間の調整や特別条項の発動手続きを適切に行うことができませんので、こちらも改善が必要です。
3、36協定の締結・周知、及び運用の見直し
法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合、又は休日出勤をさせる場合は、36協定を過半数労働組合(労働組合がない場合は過半数代表者(36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで投票、挙手等により選出する必要があります。))と締結し、労働基準監督署へ届け出ることが義務になっています。36協定がない場合は、時間外労働や休日労働をさせることができませんのでご注意ください。また、36協定があるからといって無制限に残業させられるわけではありません。
<確認すべきポイント>
● 36協定を適切に締結し、労働基準監督署へ届け出ているか。
● 36協定を従業員の見やすい場所へ掲示するなど、周知しているか。
● 実態が協定時間内に収まっているか。
● 特別条項が「常態化」していないか。
● 特別条項の発動手続きを正しく行っているか。
● 割増賃金が正しく計算・支給されているか。
特に特別条項は、本来“突発的・臨時的”な場合に発動できるものです。常態化している場合は改善が必要です。また、特別条項の発動手続きを踏んでいないケースが見受けられます。特別条項を発動するには、協定で定めた発動手続きを踏むことが必要ですので注意しましょう。
※特別条項とは・・・通常の時間外労働の上限(原則として月45時間・年360時間)を、臨時的、突発的な事情がある場合に限って一時的に超えることを認める特例の労使合意。(時間外労働は年720時間以内、時間外労働・休日労働の合計は単月100時間未満及び2~6か月平均80時間以内。原則の月45時間を超えることができるのは年6回まで)
4、メンタルヘルス対策の強化
精神障害の労災認定件数は年々増加しており、早期対応が非常に重要です。
<企業として取り組める対策例>
● ストレスチェック結果の適切な活用(高ストレス者に対する医師による面接指導の実施)
※労働者数50人未満の事業場にについても令和7年5月公布改正労働安全衛生法によりストレスチェックや高ストレス者への面接指導が義務付けられました。(施行は公布後3年以内)
● 管理職へのラインケア研修の実施
※ラインケアとは、管理職が部下の健康状態を把握し、職場の問題を改善し、不調の早期発見・早期対応を行うことです。
● 職場内でのハラスメント防止対策(ハラスメント防止や相談窓口の周知・研修実施等)
● 業務量の偏り等の把握や相談体制の整備
● 長時間労働者への医師の面接指導(対象者への積極的運用。管理監督者も対象)
メンタル不調の前兆を見逃さない体制づくりがポイントです。
5、長時間労働の早期発見とフォロー、及び事前対策
長時間労働は、放置するとメンタル不調や健康障害につながります。
時間外労働や休日労働が多い従業員の把握、年次有給休暇の取得が進んでいない従業員の把握、業務ミスや遅刻・欠勤状況、表情の変化等のラインケア等を通して、異変を早期に発見する仕組みを作りましょう。
異変を察知した場合は、業務量の調整、休息の確保(代休、年次有給休暇取得促進、勤務管インターバルの確保等)、配置転換、業務分散、面談の実施等、早急にまた柔軟に対応できる体制作りをしておくとよいでしょう。
事前対策では、心身の疲労を蓄積させない職場作りとして、年次有給休暇の計画的な取得促進、連続休暇の設定、インターバル制度の導入等も会社が取り組める有効な手段となります。また、業務の隔たり等の申告、体調不良やハラスメントの相談等、相談体制の整備・周知も大変重要となります。従業員が相談しやすい相談体制(相談窓口が適切に機能している)になっているかどうか等、定期的な検証・整備、周知等も有効だと思います。
6、まとめ
企業には、従業員の生命・健康を守る安全配慮義務があります。過重労働や健康悪化のサインを放置していた場合、損害賠償請求などの責任が生じることがありますので注意が必要です。
過労死防止は「仕組みづくり」と「早めの対応」が重要です。
厚生労働省は、過労死防止のための取組として、「長時間労働の削減、過重労働による健康障害の防止、働き方の見直し、職場におけるメンタルヘルス対策の推進、職場のハラスメント予防・解決、相談体制の整備等」をあげています。これらは過労死防止の為の取組だけではなく、従業員の定着や生産性向上にもつながる取り組みです。11月は、年末年始の繁忙に向けて、要員計画の見直し、担当者の業務偏りの是正、管理職への注意喚起等、過重労働防止の対策を実施するにも良い時期だと思います。
11月の啓発月間をきっかけに、自社の労務管理体制をあらためてチェックしてみてはいかがでしょうか。
詳細は下記、厚生労働省ホームページをご確認ください。
-
協会けんぽ 電子申請サービス開始
2025年11月5日
全国健康保険協会(協会けんぽ)が、電子申請サービスを開始することを発表しました。(令和8年1月13日サービス開始予定)
協会けんぽでは、これまで「紙」の申請書によって各種手続きが行われていました。
申請用紙を印刷して、記入して、郵送してと、手間/時間/費用をかけて手続きを行っていいましたが、今後はインターネットを通じて、パソコンやスマートフォンを利用して手続きを完了させることが可能になります。
◆申請できる方
協会けんぽの加入者(「被保険者」と一部の申請においては「被扶養者」)および「社会保険労務士」が利用可能です。
加入者の申請は、マイナンバーカードを利用して、申請者の健康保険資格情報を取得して申請します。
事前に、利用端末(スマートフォン/タブレット端末/パソコン)の準備と、マイナンバーカードの取得が必要です。
(利用できる方)
・健康保険加入の被保険者(一部の申請のみ被扶養者が申請可)
・船員保険加入の被保険者(一部の申請のみ被扶養者が申請可)
※健康保険法第3条第2項(日雇特例)被保険者及びその被扶養者は、電子申請サービスを利用することはできません。
◆対象申請書
協会けんぽが取り扱っている現金給付申請をはじめとする健康保険の主要なお手続きについて利用することができます。
◆結果等の確認
審査結果は、書面で送付されます。届いたら内容を確認してください。
・審査状況は、随時、電子申請サービス内で確認することが可能です。
・申請内容に不備があった場合は、郵送でお知らせするとともに、電子申請サービス内で申請データ等を返却します。(一部の申請では、郵送によるお知らせのみです。)
・再申請する場合などは、返却した申請データを利用して再申請することが可能です。
◆サービス提供時間
平日 8:00 ~ 21:00
・平日の上記時間外および土日祝日、年末年始12/29~1/3はご利用できません。
・17:15以降に送信完了した申請は、翌営業日の受付日扱いになります。
利用手順や操作ガイドの案内はまだ準備中となっていますので、更新されるのを待ちましょう。
詳細や注意事項は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページでご確認ください。
-
育児・介護支援における周知・意向確認等義務の整理
2025年10月3日
2025年4月・10月改正を踏まえた実務対応
育児・介護支援における周知・意向確認等義務の整理
2025年は、育児・介護休業法に基づく事業主の周知・意向確認等の義務が段階的に拡大されました。まず、2025年4月1日からは、介護離職防止の観点から、介護に直面した労働者に対し、制度内容の周知や休業取得等の意向確認を個別に行うこと、また介護に直面するよりも早い段階での情報提供が義務化されました。さらに、2025年10月1日からは育児期にある労働者について、柔軟な働き方を実現するための措置の義務化とそれに伴う制度の個別周知・意向確認、及び仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取と配慮が義務化され、事業主が対応すべき範囲は大きく広がります。もともと2022年4月から、妊娠・出産を申し出た従業員に対しての制度内容の周知と意向確認は義務化されていましたが、2025年に更に上記が追加されたことで、「どの時点で、どの対象者に、何を行う必要があるのか」がわかりづらくなっています。そこで以下に、育児・介護別に、事業主が行わなければならない周知・意向確認等の時期や内容等をまとめてみました。
施行日 区分 対象者 義務内容 周知等の時期 2022年 4月1日
育児 本人または配偶者の妊娠・出産を申出た労働者 育児休業制度等の個別周知・意向確認 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき 周知事項 ①育児休業・産後パパ育休に関する制度の内容 ②育児休業・産後パパ育休の申出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱いについて
施行日 区分 対象者 義務内容 周知等の時期 2025年 4月1日
介護 介護に直面した旨の申出をした労働者 介護休業制度等の個別周知・意向確認 介護に直面した旨の申出があったとき 周知事項 ①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等の内容 ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先
③介護休業給付金に関すること
施行日 区分 対象者 義務内容 周知等の時期 2025年 4月1日
介護 介護に直面する前の早い段階(40歳等)の労働者 介護休業制度等の情報提供 ①労働者が40歳に達する日 (誕生日前日)の属する年度(1年間)
②労働者が40歳に達する日の翌日
(誕生日)から1年間
のいずれか
情報提供事項 ①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等の内容 ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先
③介護休業給付金に関すること
施行日 区分 対象者 義務内容 周知等の時期 2025年10月1日 育児 3歳未満の子を養育する労働者 柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで 周知事項 ①事業主が選択した「柔軟な働き方を実現するための措置(2つ以上)の内容 ②対象措置の申出先
③所定外労働、時間外労働・深夜業の制限に関する制度の内容
施行日 区分 対象者 義務内容 周知等の時期 2025年10月1日 育児 本人又は配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者及び3歳未満の子を養育する労働者 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 ①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき ②労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
聴取内容 ①勤務時間帯(始業および終業の時刻) ②勤務地(就業の場所)
③両立支援制度等の利用期間
④仕事と育児の両立に資する就業条件(業務量、労働条件の見直し等)
配慮 聴取した意向について、自社の状況に応じて配慮する。 (厚生労働省の資料を元に作成)
※情報提供の方法は、いずれも共通で、面談(オンライン可)、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかです。FAXや電子メールは労働者が希望した場合に限ります。また電子メール等は、画面印刷ができるようなものである必要があります。
※申出時と周知・意向確認や意向聴取等は、上記義務とされるタイミング以外にも、労働者の状況に合わせて定期的に行うことが望ましいとされています。
今回は、改正により拡大していく義務の中でも、特に把握しにくい部分について整理してみました。周知等の時期が同じものは合わせて実施したり、対象者をリスト化する等の工夫をすると良いでしょう。会社が対応すべきことはより煩雑となっていますので、改正内容を正しく把握し、対応漏れのないように体制整備を進めていきましょう。また、育児や介護と仕事の両立は、誰にとっても身近な課題です。2025年から拡充された義務への対応は、単なる法令順守にとどまらず、従業員が安心して働き続けられる職場づくりにつながります。制度を整えるとともに、現場での理解と運用を進めていきましょう。
説明に使用する資料等、厚生労働省のホームページには多くの資料が紹介されていますので参考にされるとよいでしょう。詳細は下記をご確認ください。
-
令和7年度の最低賃金が決定しました
2025年10月3日
令和7年度の最低賃金が決定されました。
効力の発行日は各都道府県により異なりますのでご注意ください。
神奈川県の場合は、効力発生日は令和7年10月4日です。
都道府県名 引上額 令和7年最低賃金 令和6年最低賃金 発効年月日 岩手 +79 1,031 952 令和7年12月1日 茨城 +69 1,074 1,005 令和7年10月12日 群馬 +78 1,063 985 令和8年3月1日 埼玉 +63 1,141 1,078 令和7年11月1日 千葉 +64 1,140 1,076 令和7年10月3日 東京 +63 1,226 1,163 令和7年10月3日 神奈川 +63 1,225 1,162 令和7年10月4日 長野 +63 1,061 998 令和7年10月3日 静岡 +63 1,097 1,034 令和7年11月1日 福岡 +65 1,057 992 令和7年11月16日 沖縄 +71 1,023 952 令和7年12月1日 ※単位は円
他の都道府県は厚生労働省や各労働局のホームページでご確認ください。
〇最低賃金の適用される労働者の範囲
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。)
〇最低賃金の対象とならない賃金
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) 1箇月を超える毎に支払われる賃金(賞与等)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金)
(4) 所定労働日以外の労働日に対して支払われる賃金(休日割増賃金)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金計算額を超える部分(深夜割増賃金等)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当等
〇最低賃金額以上かどうかを確認する方法
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
〇最低賃金以上の賃金額を支払わない場合の罰則
最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
全国の地域別最低賃金等、詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
-
令和7年10月1日施行 教育訓練休暇給付金とは?
2025年9月2日
令和7年10月1日施行
教育訓練休暇給付金とは?
1 教育訓練休暇給付金が新設されます。
(令和6年5月10日成立の雇用保険法等の一部を改正する法律により創設)
雇用保険被保険者が、教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、賃金の一部が雇用保険から支給される制度です。
2 施行日
令和7年10月1日
3 概要
(1)教育訓練休暇給付金とは
労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付に相当する給付として賃金の一定割合を支給する制度です。
(2)支給対象者
以下の①②両方の要件を満たす一般被保険者(在職中)です。
① 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
(原則11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月)
② 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
(離職期間があっても、12か月以内であれば前後を通算できますが、失業給付等を受給している場合は通算できません。また、過去に失業手当や教育訓練休暇給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金を受けたことがある場合、通算できない期間が生じる場合があります。)
※一般被保険者とは・・・65歳未満の通常の被保険者をさします。
(3)支給対象となる休暇
以下の全ての要件を満たす休暇が対象です。
① 就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
※休暇開始前までに、就業規則等に規定されている必要があります。
② 労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇
※自発的にがポイントです。業務命令で資格を取得させる場合の休暇は対象外とされています。
※教育訓練に専念してもらうため30日以上連続して無給休暇を取得する必要があり、教育訓練休暇中に出勤を求めることはできないとされています。(例えば週に1日は出勤を求めるというようなことはできません。休暇開始時点では想定していなかった理由により結果として就労し収入を得た場合、その日については支給を受けられません。)
※収入を伴う就労を行った日(副業も含む)、教育訓練休暇とは異なる休暇・休業(有給休暇や育児休業等)を取得した日は教育訓練のための休暇とは認められず、その日については支給を受けられません。
③ 次に定める教育訓練を受けるための休暇
・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校が提供する教育訓練等
・教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
・職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)
(4)受給期間
■ 休暇開始日から起算して1年間です。
※受給期間内と所定給付日数の範囲内であれば、教育訓練休暇を複数回に分割して取得した場合であっても給付金の支給を受けることができます。ただし、期間のカウントは、最初の休暇取得日から1年間です。所定給付日数が残っていても受給期間を過ぎた場合は給付を受けられません。(妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の理由により30日以上教育訓練を受けることができない場合等で、ハローワークにより受給期間の延長を認められた場合を除きます)
(5)給付日数
■ 給付日数は、雇用保険に加入していた期間に応じて異なります。
加入期間 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上 所定給付日数 90日 120日 150日 (6)給付日額
■ 原則休暇開始日前6か月の賃金日額に応じて算定されます。
(失業給付の算定方法と同様です)
※賃金日額のほか、年齢と雇用保険に加入していた期間によっても変動します。
(7)その他 注意事項
・解雇等を予定している労働者について、教育訓練休暇給付金の支給対象となる教育訓練休暇を取得させることは認められません。万が一虚偽の申告をした場合は罰則の対象になる場合がありますので注意が必要です。
・教育訓練休暇給付を受給した場合、休暇開始日より前の被保険者期間がなかったものとみなされるため、(リセットされる)原則として一定期間は失業給付等の被保険者期間を要件とする給付金の受給ができなくなります。(ただし、育児休業給付や介護休業給付に係るみなし被保険者期間、教育訓練給付金に係る支給要件期間には影響せず、教育訓練休暇開始前の期間も通算できるとされています。)教育訓練休暇給付金を受給して間もなく自己都合退職した場合等、失業給付がもらえないケースや、勤続年数に応じて区分されている所定給付日数が少なくなる等のケースが想定されますので、その時に、知らなかった等のトラブルにならないよう、労使ともに、事前によく制度を理解したうえですすめていくことが重要だと思います。
(8)まとめ
教育訓練休暇給付金は、これまで存在しなかった「休暇中の生活費を支援する仕組み」を補う目的で新設される制度になります。従業員が安心して自主的に能力開発に取り組めるようにするために生まれたものであり、国が人材育成を後押ししている流れの一つとも言えます。
実際に休暇を取得させるとなると、その間の人員体制の確保や、就業規則の整備等、準備が必要になります。導入には一定のハードルがありますが、従業員が学び直しを通じて成長意欲を高めれば、結果的に会社の成長につながったり、企業の魅力向上につながる可能性もあると思います。また、教育訓練給付制度(教育訓練等の受講費の一部が給付される制度)との併用も、それぞれの支給要件を満たす限り可能とのことです。
新しい仕組みの一つとして検討してみてもよいのではないでしょうか。
手続き方法等、詳細は下記をご確認ください。